「ページをめくる旅」
~読書のもたらすものは?~
2025年9月24日
執筆:営業統括 西山 正人

思い起こせば、ずいぶんと昔のことになります。私は新任課長職を命ぜられ張り切って仕事をしていると自分では思っていました。ただ、慣れない環境や周囲からの様々なプレッシャー、中間管理職としてのストレスもあったのでしょうか。ある時、突然、頭がパンパンになり、仕事に関して考えることができなくなり、書類の文字を受け入れられない状況となりました。
困りました。体は元気だし、周囲も私がそのような状況に陥っているとは気づかなかったと思います。どうしたものかと訪れたのが本屋でした。文字を拒否している私の脳が興味を持って受け入れるものを探したい、そんな気持ちだったと思います。書棚の間をゆっくりと歩きながら、結局選んだのは、「すべてがFになる」という本でした。
名古屋大学工学博士、森博嗣氏のデビュー作であり、工学博士が描く密室サスペンスという設定が現在の自分と対極の位置にあるような気がして選んだのかもしれません。本当に不思議なことですが興味を持ったものは受け入れるのでしょうか、止まっていた歯車が動き出したように読むことができ、また、文字拒否モードが緩和されたような気がしました。
その後通勤途中に、同S&Mシリーズ(全10冊)を少しずつ読むようにすることで私の脳は、徐々に「ミステリー」と「ビジネス文書」の境界をつけず受け入れられるようになりました。また、謎に対し、理系的(論理的)に分析し解いていく展開がなんとなく仕事にもいい影響を与えてくれたような気がします。
英サセックス大学は2009年に、読書にはストレス解消効果があるとする研究を発表したそうです(ストレスが約68%減少)。私を困難から救った読書効果は学術的にも裏付けられていたようです。三権分立を唱えたことで有名なフランスの哲学者モンテスキューも「1時間の読書をもってしても和らげることのできない悩みの種に、私はおめにかかったことがない」と語っており、読書は心(脳)の救世主になり得るのだと思います。
私はそのころからなんとなく「いわゆる理系作家」に惹かれ、いまでも東野圭吾、安野貴博、伊予原新など愛読させていただいています。科学や、自然、技術に卓越した登場人物が、真摯な姿勢ゆえに壁にあたり、理論では解決できない葛藤を乗り越えていくストーリーに魅力を感じているのではないかと思います。
読書には、他にも「想像力が磨かれる」「問題の解決策が得られる」「視野が広がる」「教養、知識、語彙を増やせる」等々メリットもあるようですが、電車に乗っていると昔の様に本を読んでいる人はかなりの少数派になって、大多数の方がスマホを眺めているように思います。また、本との偶然な出会いが期待できる「本屋さん」も2004年には19,920店舗あったそうですが、2024年には10,417店舗に半減しているそうで、何とも寂しい話です。
GfKジャパンによる「読書頻度に関するグローバル調査(17ヵ国/2017年)」(引用元:マイナビニュース 毎日読書する人は30%、高所得ほどよく読む傾向 URL:https://news.mynavi.jp/article/20170324-a116/)によると世界読書ランキング1位中国、2位イギリス、3位スペイン、4位イタリア/米国…15位日本ということで、日本では1990年代から本離れや活字離れが指摘されているようです。「失われた30年」と言われておりますが、いろいろと大切なものを失っているのかもしれません。また、その傾向は、現在も続いており、昨年度の文化庁国語調査によると2024年、16歳以上の6割以上の人が1か月に1冊の本が読めていない結果となっています(2008年~2018年は5割程度で悪化傾向)。
最近話題となった「なぜ働いていると本が読めなくなるか」の著者三宅香帆さんは、読書の価値について、現代では効率を求め、必要な情報だけを手に入れがちですが、読書には情報に加え「ノイズ」(背景文脈や周辺知識、感情)が含まれ、この「ノイズ」を受け入れる行為が、豊かな思考や想像力を育むための必要な行為と説いています。
話は変わりますが、私が名古屋で単身赴任をしていた2008年頃にハマっていたのが「BS週刊ブックレビュー(NHK BS)」という番組でした。土曜日の早朝に放送されており、司会は児玉清さんでした。おすすめの一冊というコーナーがあり、毎週いろいろな業界から選ばれた3人のゲストが各々3冊のおすすめの本を紹介し、3冊のうち1冊は一番のおすすめとして一部の朗読を交えながら概要を紹介した後、他の書評家と司会者を交えて合評するという内容でした。つまり、このコーナーで9冊の本が紹介されるのです。
私は、この番組を見て9冊の中で読みたい本を1~2冊選び、朝食をとった後、本屋巡りをしました。選んだ本はすぐに見つかることもありましたが、3~4軒回っても見つからないこともありました。(いいウォーキングでした)とにかく歩いて1冊を手にするのです。(本の選び方はいろいろあると思うのですが私はこの出会い方が気に入っていました)残念ながら週刊ブックレビューは2011年児玉清さんがお亡くなり終了してしまいました。
なぜ、土曜の朝に本を買い、土日で本を読んでいたかというと、毎週月曜日に会社の朝礼で挨拶をする行事があり、できれば挨拶の中で、時事ネタ以外に何かしら心に残ることを話せたらということが動機でした。実際に関連付けて話せたことは少なかったのですが、出会った本をただ読むのではなく何かしらの感銘あるいは教訓などを見つけようとする体験は「知の探索」であり楽しいものでした。
名古屋のセントラルパークのベンチに腰掛け、木漏れ日を浴びながら本を読んでいた時間は忘れがたい豊かな記憶となっています。
本にかかわる番組で忘れてはならないのがNHKの「100分de名著」(現在も放送中)です。一度は読みたいと思いながらも、手に取ることをためらったり、途中で挫折してしまった古今東西の“名著”。この番組では難解な1冊の名著を25分×4回、つまり100分で読み解いていく番組ですが、テーマとなった本に対しその作者や本、思想等について詳しい方が指南役として解説いただけるのがありがたいと思います。
記憶に残っているのは「アドラー」の回です。私は書籍「嫌われる勇気」も読んでいたのですがあまり共感できずにいました。著者の岸見一郎氏が講師として「アドラー心理学」を指南いただくことで、表面(おもてづら)を流していた自分に気が付き、かつて国語の授業を受けた時のような気分を味わうことができました。
民放では、鈴木保奈美さんが司会を務める「あの本、読みました?」も楽しい番組だと思います。実際の作家や、編集者、カリスマ書店員さん等が登場し、対象の本について語るところが興味深いと思います。また、テーマ設定が秀逸で「AIと小説」とか、「三島由紀夫生誕百年」、「本屋大賞」、「辻村深月スペシャル」、等々、作家や作品の魅力がクローズアップされ、思わず本を手にしてしまいます。「コンビニ人間」を書いた村田紗耶香さんが「小説は楽譜、読者は演奏家」と表現されていたのが印象的で、読み手の可能性に言及された言葉だと思いますが、リアルな自分の人生に「小説」という楽譜を奏でることで、新たな自分を発掘することができるということなのかもしれません。
湊かなえさんの出演の際「告白」という小説の一部が紹介されました。「ほとんどの人たちは他人から称賛されたいという願望をすくなからず持っているのではないでしょうか。しかし、良いことや、立派なことをするのは大変です。では、一番簡単な方法は何か、悪いことをした人を責めればいいのです<中略>糾弾した誰かに追随することはとても簡単です。自分の理念など必要なく、自分も自分もと言っていればいいのですから」…気軽に批判可能なネット社会は小さな自己満足を増大化し、負の連鎖(ダークサイド)へ誘う社会、歯止めになるのは自らを客観視できる理性の醸成だと感じる言葉でした。
物語とは、「読んだ後に読む前の自分に戻れなくなるもの」と表現された方がいました。様々な物語を自分の人生に重ね合わせ、琴線を育む本との出会いは、人との出会いと相似です。いい本と出会い、また、いい人と出会うそんな人生を「素敵な人生」あるいは「幸せな人生」と呼ぶのではないでしょうか。
- NHK、100分de名著は日本放送協会の登録商標です。
- 嫌われる勇気は株式会社ダイヤモンド社の登録商標です。
- 本屋大賞は株式会社博報堂、本屋大賞実行委員会の登録商標です。
 メールマガジン
メールマガジン
「BizConnect」ご案内
メールマガジン「BizConnect」は、最新トレンド、新製品・サービスなど広いテーマ情報をお届けします。
きっとお客様の仕事の質の向上に繋がる気づきがありますので、ぜひご登録ください。
-
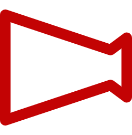
オンライン/オフラインのイベントやセミナーの開催情報をいち早くご案内いたします。
-

製品・サービスのご紹介や、新製品のリリース案内、キャンペーン情報などをご案内いたします。
-
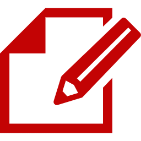
市場トレンドや、業務改善のポイントなど、今知っておきたい情報をお届けします。
ひと息つけるコンテンツも!

