「日本庭園の魅力」
~最高の日本庭園とは?~
2025年8月19日
執筆:営業統括 西山 正人
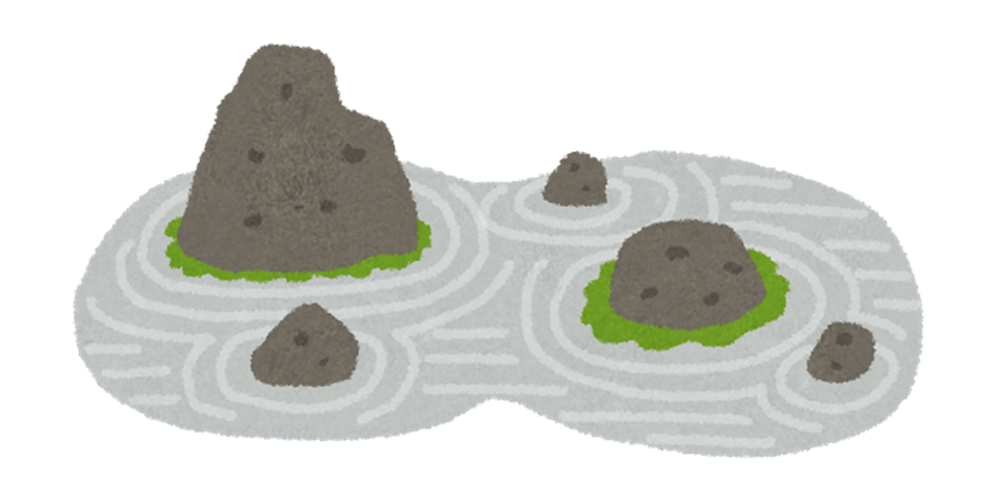
7年程前の話になりますが、私は会社の先輩に誘われ、勤務地である島根県に遊びに行きました。島根県と言えば観光に行きたい県のランキングとしては、さほど高くはありませんが、その時に訪れた「出雲大社」「松江城」「宍道湖」「美保神社」「足立美術館」等々、積み重ねられた歴史、夕日が似合う素晴らしい風景、そして人情。とても素晴らしい土地だと感じました。
その中でも、足立美術館にはとても驚きました。横山大観の絵画は120点以上所属しており、質・量ともに日本一を誇ります。他にも、竹内栖鳳、川合玉堂、橋本関雪、榊原紫峰、上村松園などが展示されていますが、なによりもその庭園が美術品と化しており、建物内から見えるその景色が一枚一枚の絵画の様に見えました。また、塵一つ落ちていないその状態に保つためにどれほどの手入れが必要なのかと感服した記憶があります。その絵画のような庭は、四季折々に異なる姿を現し、私が訪れたのは5月の新緑美でしたが、紅葉の赤、雪の白、と地元の方はそれぞれの季節の一期一会の庭の姿を楽しんでいるようでした。

足立美術館
足立美術館は、一代で財を成した島根県安来出身の実業家、足立全康氏が71歳の時に開館したそうですが「庭園もまた一服の絵画である」との信念を持ち造園に心血を注いだそうです。その結果、アメリカで発刊されている日本庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」では、22年連続で日本一に選ばれています。
当専門誌は、日本の庭を規模や知名度によらず純粋にその美と質によって評価しており、旅館や旧別荘を含む約1000の候補地の中から世界各国の専門家より選出されたランキングを毎年50位まで発表しています。選定基準から外れるのか、日本三名園である「兼六園」「後楽園」「偕楽園」は入っていないようです。
今回は、そのランキングの中で気になる名園を思い出とともに語らせていただければと思いますのでお付き合いください。
「足立美術館」がランキング不動の1位なら、不動の2位は京都にある「桂離宮」です。「桂離宮」は後水尾上皇の叔父にあたる八条宮 智仁親王によって造営され江戸初期に現在の姿となりました。現在では宮内庁の管轄ということで、HPから予約することができます。
私が訪れるに至った動機は2つあり、1つは「エースをねらえ」です。この漫画は、当時多くの人にスポーツのすばらしさや、友情、恋愛、死生観にまで影響を与えた作品だと思いますが、私もその一人です。エディ・レイノルズというオーストラリアのテニスプレイヤーを藤堂貴之が「桂離宮」を案内するシーンがあり、日本の繊細な美しさに感激するところが強く記憶に残っていました。また、もう一つはNHKのプロジェクトXです。「桂離宮」は昭和51年7月から6年の歳月と9億円の巨費、延べ4万人以上を動員して大改修が実行されました。
私の中では、プロジェクトX史上、No.1の物語です。白蟻等にやられ既に限界に来ていた「桂離宮」を、基本的にはそのまま再生改修するというプロジェクト。ドイツの建築家、ブルーノ・タウト氏が「泣きたくなるほど美しい」と称賛し、日本美の極致ともいわれた「桂離宮」の創建以来初の全面解体という大事業。大林組の現場監督と京都の名工たちとの格闘がありました。
現場監督の水本豊弘氏は責任から来るプレッシャーで、髪が一夜のうちに真っ白になりました。棟梁の川上英男氏は、図面が全て頭に入っており健康面での離脱を許されない責任を背負って、たばこをやめ車の運転をやめたそうです。柱に使われている北山杉は、木の節の位置まで計算されて配置されており、再生不可能な1本の柱のために、同じ節を持つ木を1万本の中から探し出しました。修復の技術屋、澤野直郎氏は、探し出した新木を他の古い柱の風合いに合わせるため、天井裏に積もった400年の埃を2カ月間手で擦り込み実現させました。ひび割れた白壁は、難易度が高く、現在では使われていない「パラリ壁」という技法で再現させる必要があり、左官の名工小川久吉氏は、一日100本吸っていたタバコもやめ、プライドをかけて、失敗の許されない一発勝負でやり切り、今後これ以上の仕事はできないと言って引退しました。匠たちの技と信念が結集されたドラマがそこにありました。そして永遠の美が戻ったのです。
私が「桂離宮」を訪れたのは2018年の年末でした。「桂離宮」は「池泉回遊式庭園」であり庭園の中心に池を配置し歩きながら庭園を楽しみます。20人程のグループに分けられ、職員ガイドさんから詳しく説明を受けながら1時間程広い敷地の中を歩きました。天橋立に見立てて作られた池と州浜、松琴亭という茶屋、庭園を一周したところにある古書院、中書院、新御殿と歩みを進めるたびに変わっていく景観に魅了されました。訪れたかった強い思いにしっかりと答えてくれる静謐な美しさがそこにはありました。

桂離宮
続いての庭園は、2024年度および、2003年度から9回に渡り3位にランキングされた「山本亭」です。柴又の寅さん記念館の隣にあり帝釈天からも近いとあって、大変興味があり、取材に行くこととしました。簡単に工程を記しますと、<京成金町線「柴又駅」下車⇒帝釈天参道散策⇒帝釈天⇒「山本亭」⇒寅さん記念館(併設山田洋次ミュージアム)⇒矢切の渡し⇒反省会(とらや)>といったところです。
「山本亭」は、地元ゆかりの山本工場(カメラ部品製造)の創立者である山本栄之助氏の自宅でした。建物は大正末期から昭和初期に増改築された二世帯住宅です。床の間・違い棚・明かり障子・欄間からなる書院造り、そして庭は、池泉・築山・滝などを設けた書院庭園です。部屋の中から観賞するための庭「座視観賞式」となります。座敷に座り、冷しぜんざいとお茶を頂きながら、ゆったりと庭を眺めていました。外の気温は36、7度の猛暑ですが、庭から涼しい自然の風が吹き抜け、改めて古い日本家屋の計算された居心地のよさを体感することができました。帝釈天も庭と彫刻ギャラリーを拝観することができ、寅さん記念館も含めて、癒されたい方には「柴又」を是非おすすめします。

山本亭
「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」の1位、2位、3位について、記しましたが、では、貴方はどこの庭園が好きですか?と問われると、私は、香川県「栗林公園」をあげると思います。2024年版だと15位、2011年には第3位にランキングされています。よく日本三名園と比較されてきた庭園だけに当園のランクインは誇らしい気がします。
「栗林公園」は16世紀後半には地元豪族・佐藤氏の小さな庭でしたが、1745年5代高松藩主・松平頼恭の時代に完成し以来明治維新まで高松松平家の下屋敷として使用されていました。明治8年には県立公園として一般に公開され、昭和28年には「特別名勝」に指定されました。「栗林公園」は「池泉回遊式庭園」で、「桂離宮」同様、園内を散策しながら移り行く景観を楽しみますがその多彩さは一歩、歩くごとに風景が変わる「一歩一景」の魅力があると言われています。
私が「栗林公園」を好きな理由は、結局のところ数多く訪れたから、幼いころより、色々な季節、色々な人と訪れたからではないかと思います。そのたびに「一歩一景」を感じ、新しい景色を発見してきました。偃月橋(えんげつきょう)から見た風景、錦鯉と紅葉のコラボレーション、雨に濡れた松・・・大切な記憶であり、また、何かに出会うために訪れたくなる庭園なのです。

栗林公園
日本庭園の魅力は、いつも変わらぬ美しさの提供ではなく、変わることへの感動かもしれません。自然の石を配し、池や滝などの水、そして木々、苔、築山。池はあこがれの海を模している場合もあれば、枯山水のように、水を使わずに水を表すなど、日本の自然の美を集めて表現する。精緻な設計をしていますが、完成は目指していない。三島由紀夫氏の言葉を借りれば、時間の流れを導入し終わらない庭・果てのない庭を表現し続けている。そこに最大の魅力があるような気がします。
今や海外の多くの観光客にもリスペクトされる日本の庭園。忙しさの喧騒からしばし離れじっくりと日本庭園に浸る。そのような時間があってもよいのではないでしょうか。
- NHKは日本放送協会の登録商標です。
- 北山杉は京都市森林組合他の登録商標です。
- 寅さんは松竹株式会社の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。
 メールマガジン
メールマガジン
「BizConnect」ご案内
メールマガジン「BizConnect」は、最新トレンド、新製品・サービスなど広いテーマ情報をお届けします。
きっとお客様の仕事の質の向上に繋がる気づきがありますので、ぜひご登録ください。
-
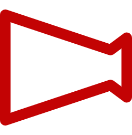
オンライン/オフラインのイベントやセミナーの開催情報をいち早くご案内いたします。
-

製品・サービスのご紹介や、新製品のリリース案内、キャンペーン情報などをご案内いたします。
-
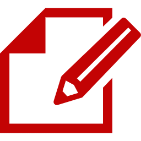
市場トレンドや、業務改善のポイントなど、今知っておきたい情報をお届けします。
ひと息つけるコンテンツも!

