「さぬきうどんに思いを馳せて」
~VS全国ご当地うどん~
2025年7月28日
執筆:営業統括 西山 正人

平成23年10月11日、香川県は、同県出身の俳優要潤(かなめじゅん)さんをうどん県副知事に起用し、「香川県は、うどん県に改名いたします」と高らかに宣言しました。こうして香川県はうどん県になったのです。
私の出身地は香川県丸亀市です。「香川県」は、古くは「讃岐」と呼ばれていました。「讃岐」は、狭貫、佐貫などとも書き、むかし、朝廷へ「調」として矛竿を納めたことから「竿調(さおつき)国」と称したことにちなむとも、東西に細長い地形から「狭貫」と書いたともいわれますが、「讃」は褒めるということ、「岐」は山の姿であることから、「讃岐」とはその美しい風土をたたえてつけた名であろうと考えられています。
観光客が抱く香川県の魅力は、讃岐の名のとおり「瀬戸内海の海や島などの豊かな自然」が64.6%でトップですが、次いで「さぬきうどん」が43.5%であり、なんと観光客の70%の方がさぬきうどんを食べているそうです(令和5年調査)。「さぬきうどん」の知名度は絶大で、香川県最強のコンテンツであることに異論はないでしょう。
その起源については、弘法大師(空海)が唐の国よりうどん作りに適した小麦と製麺技術を伝えたという伝説がありますが、その頃の麺は団子をつぶしたような形で、今のような形になったのは江戸時代と言われています。形を変えながら1200年に渡って脈々とうどん文化が引継がれ、成長してきたことになります。弘法大師は讃岐で生まれ(774年)、四国88箇所の巡礼の霊場を開設したとされており、四国の様々な文化に大きな影響を与えてきたのです。
私の中で、さぬきうどんの大きな転機は2008年「UDON(うどん)」という映画が公開されたことです。監督は踊る大捜査線を撮影した本広克行氏(香川県丸亀市出身)、主演はユースケ・サンタマリアと小西真奈美です。実在するうどん店が多数登場し、また多くの香川県出身者(要潤・中野美奈子・南原清隆・松本明子・高畑淳子・藤澤恵麻等)が出演したことでも話題となりました。瀬戸大橋記念公園でのイベントのシーンでは多くの市民(私の父も含め)がエキストラとして出演していました。なんとも華々しい「さぬきうどん」の銀幕デビューでした。
少しさかのぼると、さぬきうどんのブームのきっかけは1970年の大阪万博のブースで手打ち実演があり、万博入場者に認知されたともいわれています。1988年に瀬戸大橋が開通したこともあり、多くの観光客が香川県を訪れるようになり(観光客は倍増)、さらに認知度が上がっていったようです。
瀬戸大橋開通までは、香川県高松市の「高松駅」と岡山県玉野市の「宇野駅」を結ぶ鉄道連絡船「宇高連絡船(うこうれんらくせん)」が四国と本州を結んでいました。船上には「連絡船うどん店」があり、四国から本州へと渡るときには、うどんをすすり瀬戸内海を眺めながら何かしら故郷を背負ったものを感じ、本州から四国へ帰省するときには、乗船するや否や走ってこのうどん店に向かったものでした。特に帰省時のうどんは、帰ってきたという実感を具現化するもので、多くの香川県民に共通する感情だったのでしょう。いつも混んでいた記憶があります。宇高航路が廃止された後には高松駅に「連絡船うどん店」がオープンし、懐かしの味を継承していましたが2021年に閉店したようです。私の記憶では、この連絡船うどんは麺にさほど「こし」はなく、他のさぬきうどんと比べて決して特出したものではありませんでしたが、<郷愁><瀬戸内海><連絡船>などが交わった思い出の味覚だったのではないかと思います。
思い出ということであれば、大晦日の年越しは、「うどん」と「そば」の両方がありました。そばを年越しに食べる習慣は諸説ありますが、そばは細く切れやすいことから、1年間に起きた厄災や苦労を切り捨てて翌年に持ち越さず、気持ちよく新年を迎えるために食べられてきたようです。「縁切りそば」や「年切りそば」と言われることもあるようです。一方うどんには「運を呼ぶ」や、形状にちなんで「太く長く」といった願いが込められています。つまり、大晦日に両方食べるのはずいぶん贅沢な過ごし方だったのだと思います。
話を戻しますと、2000年に入り地元チェーン店である「はなまるうどん」や「めりけんや」が東京に進出し、また丸亀の名前を広めた「丸亀製麺」が兵庫県加古川市に初号店を開店させました。日本国内には色々なご当地うどんがあり、その中で「さぬきうどん」が名前を広めたのはその独特のコシと風味も含めた品質の高さにあると思いますが、チェーン店化し全国展開されたことでさらに認知度が高まったと考えられます。また、現在の丸亀製麺はDXでも有名で、業務システムはSaaS化し、バックオフィスの定型業務はアウトソーシング、AI需要予測にも取組んでいます。バックオフィス業務・現場のマネージメントを徹底して省力化し、空いた時間を接客業務(感動体験)に費やすことで価値を高めています。また、DX推進の結果、出店も含めてスピーディで効率的な事業展開を可能としているようです(店舗数1,104店/内840店日本)。
さて、さぬきうどんについて話を進めてきましたが、ここで少し、うどんの起源やその他のうどんについて触れたいと思います。うどんの起源は古代中国に遡り、奈良時代に日本に伝わったとされています。当時のうどんは「索餅(さくべい)」と呼ばれる小麦粉を練って作ったもので、現在のうどんとは異なる形状でした。平安時代になると、うどんは「饂飩(うんどん)」として文献に登場し、次第に日本各地で親しまれるようになりました(諸説あり)。
全国のうどんの中で、日本三大うどんと言えば「さぬきうどん」「稲庭うどん」「水沢うどん」とされています。
「稲庭うどん」は秋田県湯沢市稲庭町で作られる細めのうどんです。江戸時代初期に発祥し、藩主への献上品としても知られています。製法は「手延べうどん」で、これは粉を練り上げてから生地を棒状にし、手でよりをかける「手綯い(てない)」とそれを更に延ばす「延ばし」という工程を経て、細い麺にするやり方です、この製法では「五島うどん(長崎)」「氷見うどん(富山県)」が相当し、遣唐使により五島に伝わった後、北前船で日本海を北上したという説があります。
実は私が東北で勤務しはじめた頃、秋田県のビジネスパートナーの方と「さぬきうどん」VS「稲庭うどん」でうどん論争となり、「なにが讃岐だ、うどんと言えば稲庭だろう!」とお叱りを受けたことがありました。地産の名物はその土地のアイデンティティであり、またプライドでもあります。トラの尾を踏んだ私は、「日本酒」VS「焼酎」論争も絡まり、ずいぶんとたくさんのお酒を飲むに至りました。

さぬきうどん
では、「水沢うどん」ですが、群馬県渋川市の水沢地区で作られています。さぬきうどんと同様製法は「手打ちうどん」。これは、粉を練り、こねてコシを出し、生地を延ばして切る麺を使います。飛鳥時代に水澤観世音の創建に尽力した高麗からの渡来僧がうどんの製法を伝授したと伝わっており、天正4年(1576年)頃に湯治客や参拝者に地元産の小麦と水沢の湧水で打ったうどんを供するようになったのが始まりとされています。実は「水沢うどん」は食べたことはなく、この度取材に行ってきました。水澤観世音の近くにはうどん屋が並んでおり、伊香保温泉につながる観光ルートとなっているためか大変盛況でした。うどんそのものは、さぬきうどんより少し細麺で同様のコシがあり、大変おいしくいただきました。

水沢うどん

水澤観世音
日本三大うどんに触れましたが、全国には著名なご当地うどんが数多くあります。ざっと北から並べますと【秋田県】稲庭うどん【栃木県】耳うどん【群馬県】水沢うどん/ひもかわうどん【埼玉県】川幅うどん/武蔵野うどん【山梨県】吉田のうどん【愛知県】豊橋カレーうどん/味噌煮込みうどん/きしめん【三重県】伊勢うどん【富山県】氷見うどん【大阪府】かすうどん【岡山県】津山ホルモンうどん【香川県】さぬきうどん【福岡県】博多うどん【長崎県】五島うどん、等々…
私は残念なことにこの中でも半分くらいしか体験できておらず、今後更に変化/進化してゆくであろう「ご当地うどん」にも注目して、百名山ではありませんが、「旅行」+「食べ歩き」を楽しんでいきたいと思います。
皆さんも気になるご当地うどん店に足を運ばれてはいかがでしょうか。
- うどん県は香川県の登録商標です。
- はなまるうどんは株式会社吉野家ホールディングスの登録商標です。
- めりけんやは株式会社めりけんやの登録商標です。
- 五島うどんは五島手延うどん協同組合の登録商標です。
- 豊橋カレーうどんは豊橋商工会議所の登録商標です。
- 伊勢うどんは三重県製麺協同組合の登録商標です。
- 水沢うどんは、水沢うどん商標登録店組合の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。
 メールマガジン
メールマガジン
「BizConnect」ご案内
メールマガジン「BizConnect」は、最新トレンド、新製品・サービスなど広いテーマ情報をお届けします。
きっとお客様の仕事の質の向上に繋がる気づきがありますので、ぜひご登録ください。
-
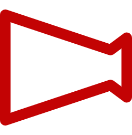
オンライン/オフラインのイベントやセミナーの開催情報をいち早くご案内いたします。
-

製品・サービスのご紹介や、新製品のリリース案内、キャンペーン情報などをご案内いたします。
-
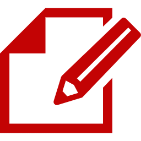
市場トレンドや、業務改善のポイントなど、今知っておきたい情報をお届けします。
ひと息つけるコンテンツも!

